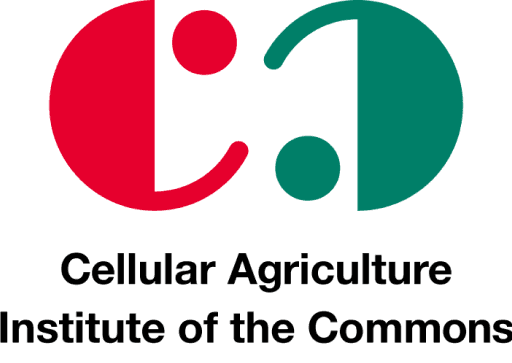担当者 日本細胞農業協会アナリスト 小池樹音、西川優嗣
1. はじめに
細胞農業のような研究開発段階にある食品技術において、公的機関の研究費は重要な役割を担っている。しかしながら、これまで日本の細胞農業に関する研究開発状況を研究費の観点から調べた情報源は限られていた。そこで本調査では、国内の研究費がどの程度細胞農業に割り当てられているかの実態を把握し、日本における細胞農業の研究状況を明らかにする。本報告が、細胞農業分野における今後の研究の指標や今後の幅広い機関における研究費策定の意思決定における一助となれば幸いだ。
2. 調査概要
2024年11月に、細胞農業を下記の6つのカテゴリーに分け、研究題目に対する研究費の内訳と、各カテゴリーにおける総費用を調査した。
- 培養肉
- 培養魚
- 精密発酵
- 培養乳
- 培養ミルク
- 植物(植物性タンパク質・代替肉、分子農業)
- 代替タンパク質
調査対象とする研究の選定にあたって、各カテゴリーについて以下の基準を設けた。
科研費の場合
- 培養肉
研究タイトル、研究開始時の研究の概要、研究実績の概要に「培養肉」「培養食肉」が含まれているもの。 - 培養魚
研究タイトル、研究開始時の研究の概要、研究実績の概要に「培養魚」が含まれているもの。 - 精密発酵
研究タイトル、研究開始時の研究の概要、研究実績の概要に「精密発酵」が含まれているもの。 - 培養乳
研究タイトル、研究開始時の研究の概要、研究実績の概要に「培養乳」が含まれているもの。 - 培養ミルク
研究タイトル、研究開始時の研究の概要、研究実績の概要に「培養ミルク」が含まれているもの。 - 植物
「植物性タンパク質」「代替肉」「細胞農業」「代替タンパク質食品」「分子農業」「植物性代替肉」といったキーワードで検索し、関連性が高いと判断されるもの。 - 代替タンパク質
上記4つのカテゴリーに重複して該当するもの。
科研費以外の助成金
それぞれのカテゴリーに該当し得るものを協議の上選択した
3. 調査結果
本調査の結果、細胞農業に該当する研究題目として計40件が確認された。以下に「培養肉」「培養魚」「培養乳」「培養ミルク」にカテゴライズされた研究題目を示す。「代替タンパク質」「植物(植物性タンパク質・代替肉、分子農業)」については添付したGoogleスプレッドシートにてご確認いただきたい。尚、調査には主に科学研究費助成事業(科研費)のデータベースを使用したが、その他の助成金に関しては研究費が明記されていない場合もあり、その場合は「非公開」と記載した。
表1 細胞農業に関する国内研究費の一覧

*注) 一部助成金は公表されてる満額の金額で実際の額と異なる場合があります。
ダウンロードはこちらから↓↓
日本細胞農業協会 国内研究費
更に、表1から国内研究費を培養肉、培養魚、精密発酵、培養乳の4つのカテゴリー毎に合算した。
表2 各カテゴリーごとの研究費の総計とその割合

*注) 今回は細胞農業に特化した割合を示すため「植物/代替タンパク」は除外しております。また、「培養ミルク」は研究費未記載のため掲載しておりません。
4. 考察
1)培養肉の研究状況
表1の「期間開始」の項目から、日本では培養肉に関する研究が2016年以降 本格的に開始されていることが確認された。研究代表者の所属学部からは、その後工学、医療、経済、社会学といった多様な視点から、培養肉の開発や解明に向けた取り組みが進展していることが伺える。また、表2の国内の研究費総額においても、細胞農業全体に対して培養肉の研究費は約99.7 %と圧倒的に高い割合を占めている。さらに、今後も継続的に研究が予定されている題目が確認されたことから、培養肉は日本国内で積極的に研究が進められている細胞農業の分野であるといえる。
2)培養魚の研究状況
しかし、培養魚に関する研究は極めて限られていることが判明した。表1より、現在進行中の研究の一例として、北里大学海洋生命科学部の池田大介准教授が培養二ホンウナギの研究が挙げられる。
3)精密発酵及び培養乳・培養ミルクの研究状況
更に、精密発酵という単語を使っている研究実績については、本調査でヒットしたものはなく、この分野・単語の認知度が低い(全国で約15%)ことも影響している可能性がある(精密発酵に関わる認知度、試食意欲および最適な呼称の調査)。一方で、北海道大学農学部の小林謙准教授は「培養乳」、大阪大学大学院工学研究科松崎典弥教授は「培養ミルク」の生産技術に関する研究を進めていることが確認された。
5. 総括
これらの結果から、日本では培養肉の分野で一定の研究進展が見られる一方、精密発酵の分野に特化した研究は見られないことがわかった。培養魚や培養乳に関しては、少数ながら進められているようである。今後は、コスト削減や規制整備、消費者意識の向上といった課題解決に向けた、細胞農業の研究進展が予想される。
※当記事又はデータを使用する際は「日本細胞農業協会」をクレジットに記載してください
また、質問のある方は以下のメールアドレスにお問い合わせください