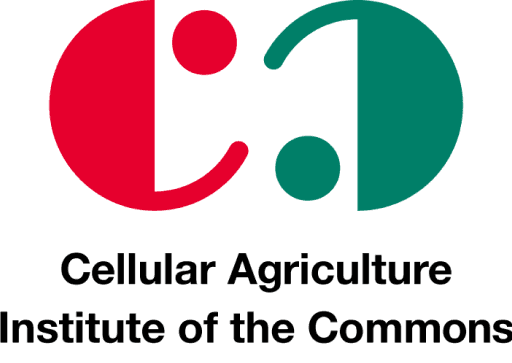培養食料生産の現在地を知る
-「第3回細胞農業会議」レポート-
細胞を培養することで、持続可能な食料生産を目指す「細胞農業」の取り組みは、社会の食肉需要や環境意識の変化などを受け、その裾野がますます広がりつつあります。去る2021年8月29日、この細胞農業に取り組む研究者同士が繋がり、議論と情報交換することを目的に、第3回細胞農業会議がオンラインで開催されました。当日は、国内外で細胞農業の研究、関連する技術開発、ルールメイキングなど社会実装に取り組む研究者らが登壇。最新の知見が紹介されるとともに、パネルディスカッションやショートプレゼンなどを通し、将来の可能性についての深い議論も行われました。
冒頭では開会に先立ち、会議を主催する日本細胞農業協会理事長の五十嵐圭介氏が登壇。『細胞農業はこれまでに例のない取り組みである為、技術開発やルールメイキングだけでなく、消費者の方々への受容性の開拓や既存の食肉産業に関わる農家さんなど、様々な分野との連携が不可欠。今日のこの場が、色々な分野の方々のコラボレーションが生まれる場になって欲しい』と期待を述べました。その後、我が国の細胞農業技術を牽引する研究者による基調講演と、シンポジウムが続けて行われました。
細胞培養による食肉生産「食肉3.0」
トップバッターは東京大学の竹内昌治(たけうち しょうじ)教授。竹内教授はまず、細胞培養による食肉生産「食肉3.0」の背景として①食肉の枯渇、②食肉の生産に係る環境負荷、③感染症を防ぐための抗生物質の多用、④動物福祉やフードロスなどの倫理的な問題の4点があると説明。そのうえで安全性が高く、環境負荷の低い代替肉の需要が高まっていると述べました。食用の培養肉も、広義にはこの代替肉の一種とみなすことができます。その中で竹内教授の研究グループが目指しているのは「本物志向の培養肉」、つまり厚みのある3次元の肉組織を、細胞だけで作製することです。
ここで「肉」とは何なのか?という素朴な疑問について考えてみましょう。例えば「牛肉」は牛の筋肉、「鶏肉」は鶏の筋肉です。竹内教授はこの「筋肉」の特徴を再現することが、培養ステーキ肉の作製に重要なポイントになると考えています。竹内教授のグループでは、格子状の鋳型に細胞とコラーゲンを混ぜ合わせたものを流し込み、モジュールとして積み重ねることで、筋肉に特徴的な縞状構造(サルコメア)を持つ立体的な組織を作製することに成功しています。さらに、この組織の培養日数を増やしたり、電気刺激によって収縮させたりすることで、食感を実際の肉に近づけられることを確認しました。今後の技術面での課題としては、まずは実際に食べられる組織を作ること、さらに組織の強度を保ちつつ、よりコストのかからない作製法を模索することが挙げられます。
一方で竹内教授は、培養肉の普及には文化面での課題の解決も必要だと語ります。『いくらいいものを作っても、それが社会に受け入れられなければ意味がない。その為には文化をいかに醸成するか、規制をどうするのかを考える必要がある』と指摘しました。
藻類を用いた持続可能な培養液の生産
二人目の登壇者は東京女子医科大学の清水達也(しみず たつや)教授。もともと再生医療を専門とする清水教授の話題は、細胞培養に必要不可欠な培養液について。培養液には、糖やアミノ酸、ビタミンなど、細胞が生体の外で生きていくために必要な栄養素が含まれています。しかし、これらの栄養素は『その多くが穀物から生産されるため、結局は畜産と同様、環境への負荷が大きくなっている』(清水教授)。現在、培養肉1キログラムにつき50リットルの培養液が必要なため、大量生産時にはより多くの穀物が消費されるという予測があります。また、市販の培養液には成長因子という細胞の増殖を促す成分が含まれていますが、これらは食用としては用いることができないため、そのまま使うことは難しいのが現状です。
そこで清水教授が新たな栄養素として着目したのが、クロレラやユーグレナといった藻類。地球上の食物連鎖のスタートに位置する藻類は、自ら光合成を行い様々なエネルギー源を作り出す能力を持ちます。また、穀物と比べすぐに量を増やせること、サプリメントやバイオエタノール生産などで、社会での応用の知見が積み重なっていることも強みだといいます。清水教授の研究グループでは、様々な種類の藻類を加水分解した結果、その多くで培養液の基本成分となる糖、アミノ酸、ビタミンが抽出できることを発見。さらにこれらを用いて、牛の筋肉由来の細胞を、その増殖能力を保ったまま市販の基礎培地とほぼ同じ期間生存させることに成功しました。
また、現在清水教授は「培養液のリサイクル」というアイディアも着想し、実験を進めています。具体的には、動物細胞の培養時に大量に発生する廃液を、藻類の培養に再利用しようというものです。実は、動物細胞を培養した後の廃液には、細胞の生存に使われなかった栄養素がある程度残っています。そのため、これらを用いて藻類を増殖させることができるのです。清水教授は、こうした藻類の培養系と、動物細胞の培養系を組み合わせ、循環型の培養肉生産の装置化を目指しています。清水教授はこのシステムについて『従来の食料生産に比べ省スペース化が可能と考えられる。そのためこれまで食料自給が難しいと思われていた飢餓地域などでも稼働できるのではないか』と可能性を語りました。
続いてのシンポジウムでは、自身の研究を細胞農業へ展開する可能性について模索する3人の研究者が登壇し、それぞれの研究テーマとその展望を語りました。
3Dプリンターで未来食をつくる
山形大学の古川英光(ふるかわ ひでみつ)教授は「3Dプリンターで未来食を創る」と題して、自身が取り組んでいるゲル加工技術について発表しました。柔らかさと安定性を兼ね備えるゲルは、医療から工業まで幅広く応用可能な素材として、また細胞が生存・増殖する足場の材料としてよく用いられています。これまで3Dプリンターを用いて食品や歯車など様々なものを成形してきた古川教授は、光を照射すると固まる光硬化樹脂を使ったものづくりを紹介。3Dプリンターから吐出された材料をその場で成形することで、より高精度の造形が可能になりうると展望しました。
蛍光/生物発光タンパク質が変革する細胞農業
蛍光タンパク質とその技術応用の専門家である大阪大学の永井健治(ながい たけはる)教授は、「蛍光/生物発光タンパク質が変革する細胞農業」と題して発表。先の清水教授の講演に関連し、植物や藻類の効率的な光合成を促進する為に有用な蛍光タンパク質について複数の研究成果を紹介しました。そもそもほとんどの植物は、緑色の光を光合成に用いることができません。そこで永井教授が発想したのが、蛍光タンパク質を用いて、緑色光を光合成に使用可能な赤色や青色の光に変換するというもの。こうすれば、植物はより光を効率的に利用してエネルギーを生産できるようになります。実際にこの蛍光タンパク質を発現した植物を育てたところ、通常の条件に比べて重量比でおよそ5倍の大きさにまで成長させることが可能になりました。永井教授はさらに、夜間に自ら放つ光をもとに、自力で光合成を行う植物のアイディアも披露。これらの技術で、藻類や植物の増産が容易となり、低コストかつ高効率な細胞食料の生産が可能になると語りました。
自己組織化技術でレバー, フォアグラをつくる
東京医科歯科大学の武部貴則(たけべ たかのり)教授のトークのテーマは「肝臓」、肉の部位でいえばレバーについて。武部教授は研究にあたり『レバーの独特の味や食感はなぜ現れるのか?そもそもレバーが、レバーたりえるには何が必要なのか?』という疑問を抱いたといいます。肝臓の細胞は培養がとても難しいとされていますが、武部教授は柔らかいゼリー状の基盤に、細胞間を繋ぐ間質という組織を組み合わせて細胞を培養する「自己組織化」技術を考案。肝臓由来の細胞を実際の臓器のように立体的に成長させ、血管様の構造までも形成できたそうです。この技術を用いれば、理論上はあらゆる肉の部位を再現することが可能となります。武部教授のグループは脂肪肝構築のスペシャリストであり、その技術を生かせば、将来は脂肪成分の量や種類を調節した「痛風になりにくいフォアグラ」を作ることも可能になるかもしれません。
パネルディスカッション~培養食料の実現に向けて~
基調講演とシンポジウムの終了後は、登壇した5名の研究者により、培養食料の実現に向けたパネルディスカッションが行われました。
まず竹内教授が、細胞を立体的に培養する技術として、ボトムアップ型のオルガノイドや、トップダウン型の3Dバイオプリンタという2つの方法について『今後の食用化を見据えて、オルガノイドはどうやってサイズを大きくしていくのか、3Dプリントはどうやってゲル中の細胞密度を上げて、内部形態をリアルに作っていくのか』と問題提起しました。これに対しまず武部教授が『ある程度のところまで完璧なオルガノイドを作ることができれば、そこから先は溶液の流れや酸素、栄養の供給といったインフラを整えることで自然に成長するのではと考えている。我々が元になるオルガノイドを作ることができれば、そこから先はエンジニアリングを組み合わせていけばかなり大きなものが作れるのではないか』と述べました。また古川教授は『培養にあたり、細胞が住みやすい構造体を作るためには、光を用いた造形の解像度を上げる必要がある。その点では永井教授が取り組まれている、光を用いたテクノロジーがカギになってくると思う』と、光学の知見の重要性に言及しました。
これを受けて永井教授は、自身のグループで3Dプリンターを用いて蛍光を発する樹木の造形を試みていることを紹介。そのうえで『発光する細胞を、樹木のようにメートル級の大きさにするにはどれくらいかかるか、またそれらを成長させるためのエネルギーをどう確保するかの方策についてご意見を伺いたい』と質問しました。これに対し古川教授は『ある程度の大きさの細胞の塊を育てることは現在でも出来ているので、それらをモジュールとして積み上げるアプローチがありうる。また、無限に得られる太陽光のエネルギーを、細胞生育などのインフラを動かすために利用することも今後考えられる』と期待を示しました。
後半の一般演題でも、興味深い発表が複数行われました。
3Dプリンターでサシ入りステーキ肉をつくる
大阪大学の松崎典弥(まつさき みちや)教授は、3Dプリンターを用いて、筋組織だけでなく脂肪組織や血管組織を持つ培養肉の生産を目指しています。天然の肉と同じように複数の組織を混在させるためには、それらを適切に配置することが重要です。松崎教授のグループは、細胞溶液が拡散せず最適に配置されるような3Dプリント技術を考案。分化した筋線維、脂肪組織、血管組織ファイバーを持つ、構造化された培養肉の作製に成功しました。
細胞農業におけるルール形成戦略と今後の課題
細胞農業研究会広報委員長の吉富愛望アビガイル(よしとみ めぐみ -)氏は『細胞農業におけるルール形成戦略と今後の課題』と題して発表。吉富氏は、現在の日本で細胞農業産業全般に関するルールが整っていないことを指摘し、その策定の意義について「食領域における日本のブランド力の維持」「先行者優位の獲得」「食料安全保障の確保」「カーボンニュートラル目標の達成」の4点にあると説明。その上で細胞農業研究会として、農林水産省をはじめとする関係省庁や既存の食産業とも連携し、法律やガイドラインの策定に参画していることを明らかにしました。
以前、培養肉に関するシンポジウムに参加した際も、様々な取り組みが行われていることに感銘を受けましたが、あらゆる面で確実にこの領域が進展していることを改めて実感できました。また、今回の研究会は登壇者も含め400名以上の参加者があり、一般の方々も含めてますます関心が高まっていると言えます。今後これを、それぞれの研究のさらなる発展と応用、また培養食料が社会的に受け入れられる機運の醸成につなげることができるか、注目されます。