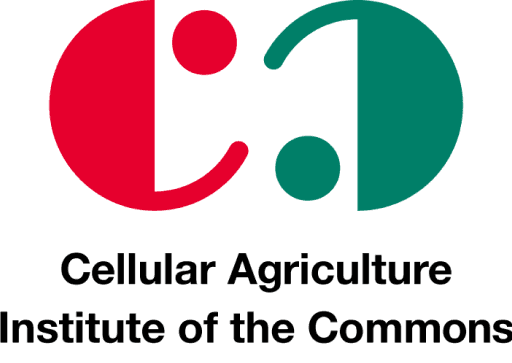はじめに
2022年11月、米国食品医薬品局(FDA)は、UPSIDE Foods社の培養鶏肉の安全性について、安全であるという同社の結論に現時点で異議はない旨を発表しました。実際の販売にあたっては、さらに他の要件を満たす必要がありますが、近い将来、培養鶏肉が米国市場で販売される見通しが高まっています(参照:https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-completes-first-pre-market-consultation-human-food-made-using-animal-cell-culture-technology)。
また、シンガポール食品庁は2020年12月に培養鶏肉の販売を承認しており、すでにシンガポールでは培養鶏肉を使ったチキンナゲットやチキンサテーを食べることができます。
このように海外では、法律上の手続を経て、細胞性食品(いわゆる「培養肉」等)が市場で販売される動きが進んでいます。
それでは、日本における細胞性食品に関する法令等やルール形成の動向はどのようになっているのでしょうか。
現在の日本の状況
2023年1月19日現在、日本には、細胞性食品に焦点を当てた法令等は存在していません。
また、海外には、EUやシンガポールなど、細胞性食品等の新しい食品の販売に関する事前承認制度が設けられている地域もありますが、そのような制度も日本には存在しません。
したがって、日本においては、現時点では、細胞性食品だけではなく広く一般に適用されている既存の法令等が、細胞性食品の場合にどのように適用されることになるのかが重要な問題といえます。
もっとも、細胞性食品が実際に食品として販売される可能性が高まってきたのはごく最近のことです。そのため、細胞性食品が既存の法令等においてどのように位置付けられるのかは明らかではありません。既存の法令等の適用や運用に関する議論を含め、細胞性食品を念頭に置いた具体的なルール整備に関する議論は今まさに行われている段階です。
法律上の論点と関連する法令等
まず、細胞性食品に関連する可能性のある既存の日本の法令等としてどのようなものが考えられるでしょうか。また、細胞性食品に関して、それぞれの法令等において、何が論点となるのでしょうか。
以下では、網羅的ではありませんが、大まかな全体像を概観してみます。ここでは、「食品安全」「食品表示」「知的財産としての保護」を取り上げます。
食品安全
まず、細胞性食品の安全性をどのように確保するのかが大きな法律上の論点といえます。
食品の安全性に関連する既存の法律としては、例えば、「食品衛生法」があります。
この法律では、食品一般について、安全性を確保するために公衆衛生の観点から必要な規制が定められています。例えば、食品の販売禁止措置や、食品や添加物の製造等に関する基準等についての規定が定められています。
(安全性についての議論はこちらのコラムもご参照ください:【寄稿】 培養肉に関する法規制
と、日本における安全性の保証について)
食品表示
細胞性食品を販売するに当たってパッケージ等に表示すべき事項や、表示の方法も重要な論点です。
食品に関する表示についての規制としては、「食品表示法」や「食品表示基準」があります。
また、商品やサービスの取引に関連する不当表示の禁止等について定める「景品表示法」にも配慮する必要があると思われます。
知的財産としての保護
細胞性食肉は、種細胞を育成し、細胞を増やした後に肉の形に成形(=立体組織化)することで作られます。
この細胞性食肉の生産過程の起点となる種細胞について、付加価値があるものを知的財産としてどのように保護すべきかが論点となっています。その他にも、細胞性食品の生産や販売に関連する知的財産をどのようにして保護していくかが、とりわけ細胞性食品に関するビジネスを行う場合には、重要な法的問題であると思われます。(参照:細胞農業の生産過程)
日本国内のルール形成動向(2022年12月現在)
次に、日本国内における細胞性食品に関するルール整備に関してどのようなアクターがどのような活動を行ってきたのかを概観します。
行政
農林水産省では、2020年4月に「フードテック研究会」が立ち上げられ、同年7月には「中間取りまとめ」が公表されました。さらに、同年10月に「フードテック官民協議会」が立ち上げられ、細胞農業を含めたフードテックに関連する分野について、産官学での議論が行われています(参照:農林水産省ホームページ)。細胞農業分野では、細胞農業WT(ワーキングチーム)において、ガイドラインや政策提言書の作成に向けた議論が行われてきました。また、日本細胞農業協会も細胞農業CC(コミュニティサークル)の事務局として、細胞農業による生産物の社会受容を目指した活動を行ってきました。
厚生労働省では、細胞性食肉等の新開発食品について、最新の科学的知見や海外の取組状況等の収集及び安全性確保に係る検証が実施されています。
また、経済産業省でも経済産業省フードテック若手有志チームが立ち上げられ、フードテックの振興を目指した活動がされているようです。
政党・議員連盟
政党や議員連盟に関する動きとしては、2021年6月に自民党内で「『細胞農業および培養肉』についての勉強会」が開催され、議員連盟の設立が決定されました。2022年6月には、自民党の有志議員により「細胞農業によるサステナブル社会推進議員連盟」が立ち上げられました。この議員連盟では、細胞性食品の早期の市場化に向けた提言等を行っていくとみられます。
民間
民間では、フードテック官民協議会の細胞農業WTの事務局も兼ねる多摩大学ルール形成戦略研究所の「細胞農業研究会」が、2022年11月にルール整備に関する提言書を作成し、関係省庁に提出しました。また、細胞農業研究会は、提言書の提出を機に、一般社団法人へと改組されました。
おわりに
このように細胞性食品に関連していくつも重要な法律上の論点があり、また、ルール整備に関しても、行政、政治、民間の分野で様々な動きが見られます。
関連する法令等を理解しておくとともに、ルール整備に向けた議論を注視していくことは、細胞性食品に関するルール整備の議論に参加するためにも、あるいは将来細胞性食品に関するビジネスを行うためにも、とても有意義であると思われます。
※本コラムの見解は筆者が所属する法律事務所の見解ではありません。