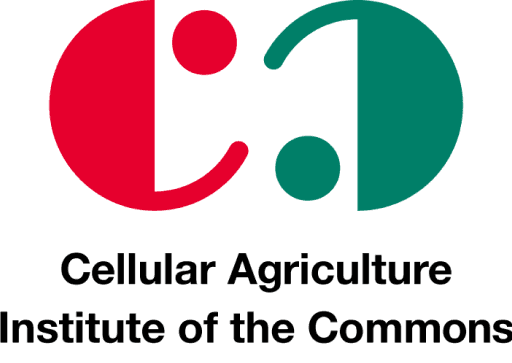培養肉や培養シーフードは、見た目こそ普通のお肉や魚の身と変わりませんが、その作り方は従来の食品とは全く異なります。ですから、培養肉や培養シーフードはもしかすると人間の体に害を与えるものかもしれません。
そのため、細胞培養食品を販売し、多くの人に食べてもらうためには、「食品として安全であること」が何らかの形で保証される必要があります。
一般的に、こうした食品の安全性を保証するのは国の役割です。日本には食品衛生法という法律があり、人間の体に危害を与えるような食品や食品添加物などは販売できないように規制されています。
では、細胞培養食品を日本で販売する場合、その安全性はどのように保証されるのでしょうか。これは、我々が今後、安心して培養肉や培養シーフードを食べるために考えなくてはならない重要な問題です。
少し難しい話も出てきますが、ここでは可能な限り簡単にこの問題について考えてみたいと思います。
ただし、本題に入る前に1つお断りしておきたいのは、日本でまだ細胞培養食品は販売されていない以上、この答えは、まだ誰にも分からないということです。現在、日本でも細胞培養食品の規制について議論が進んでおり、いずれその結論は出るのですが、少なくとも現段階では明確になっていません。ですから、ここから先の話はすべて現段階で考えられる可能性に過ぎないことにはご留意頂きたいと思います。
日本において、法令上原則として培養肉の販売は自由という解釈もできる。しかし、安全性を保証するための仕組みが必要
では、日本での培養肉にまつわる法規制を考えてみましょう。日本の食品衛生法には「これまで人間が食べてこなかった全く新しい食品」を規制するためのルールが存在しています。このルールは食品衛生法の第7条で定められており、以下にその条文を一部引用します。
厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかった物であって人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなった場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するための必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。(食品衛生法7条1項)*
要約すると「これまであまり人間が食べた経験がなく、『健康に害はない』という確証がない食品が販売される場合、予防的にその食品の販売は禁止されることがある」ということが定められています。
つまり、「この食品はこれまでにない新しいもので、もしかすると健康に害があるかもしれない」となった時に、その食品の販売を禁止できるというわけです。この7条1項の規制の対象となる食品は、新開発食品と呼ばれています。
ここから分かることは一体何でしょうか?1つ言えるのは、日本の法律上は「新開発食品の販売は原則として自由に行ってよい」ということです。
食品衛生法のルールは、「もし問題がある場合には、新開発食品の販売を禁止できる」という趣旨ですから、原則は新開発食品の販売は自由に行えます。もっとも、先の7条1項の規定は、食品と健康被害との間の因果関係が多少薄くても適用できると解釈されているので、「自由に販売できる」と言ってもその程度には注意が必要です。
ただ、とにかく原則論は「自由に販売できる」ということになります。このように、原則としては販売を自由に認めつつ、例外的に規制するものを個別にピックアップする方法をネガティブ・リスト方式と言います。「ネガティブ」、つまり“ダメなもの”をリストアップするということです。日本での新開発食品のルールはネガティブ・リスト方式ですから、培養肉などの販売も原則的には自由であると言える可能性もあります。
これに対して、原則として新規食品の販売は禁止で、特別に認められたものだけに販売を認めるという方法もあります。これをポジティブ・リスト方式と言います。外国での状況を見ると、先進国の多くがポジティブ・リスト方式の規制を採用しています。
例えば、世界で初めて培養肉が販売されたシンガポール。シンガポールでは、少なくとも過去20年の間に一般的に提供されていたことがない食品については、販売の前に安全性を評価した報告書を政府当局に提出することが義務付けられています。アメリカでも、培養肉を販売する場合には事前に政府当局と協議して、その生産過程が監視されることになっており、EUでも新開発食品の販売には事前の認可が必要となります。
こうして見ると、「日本の規制って甘いんじゃないの?」と心配になってしまうかもしれません。そこで次は、日本で培養肉などの安全性を事前に保証するための仕組みの可能性を考えてみましょう。
日本で培養肉の安全性を保証する仕組みを、遺伝子組換え食品をヒントに考える
ここまで「培養肉などは原則として自由に販売できるかも?」ということをお話してきましたが、これでは少し不安な部分もあります。日本でも、何か事前に規制する方法はないのでしょうか。
もちろん、法律を変えるというのが一番手っ取り早い策かもしれません。しかし、法律を改正するとなると、これは国会も巻き込んだ大変な作業になります。法律を変える以外に何か方法はないのでしょうか。
ここで参考になるかもしれないのが、遺伝子組換え食品に関する規制です。
遺伝子組換え食品も細胞培養食品と同じように、外形的には普通の食品と変わらないものの、その生産方法が特殊な食品です。そのため、遺伝子組換え食品も人間の健康に危害を与える可能性があるということで、その販売は法律で規制されています。
ただし、先ほどから見ているように、食品衛生法7条のルールでは事前に規制をかけることは難しい。そこで、遺伝子組換え食品の規制で用いられているのが、同じく食品衛生法の13条のルールです。
この13条の条文も確認してみましょう。
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。(食品衛生法13条1項)*
前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。(食品衛生法13条2項)
要約すると、食品衛生法13条1項では、市販される食品や添加物の生産方法などに関する規格を定めた「食品、添加物等の規格基準」を厚生労働大臣が策定できるとされています。そして、この「食品、添加物等の規格基準」に合致しない食品などは販売してはいけないということが、13条2項で定められています。
そして、遺伝子組換え食品については、この「食品、添加物等の規格基準」のなかで「遺伝子組換え食品を販売する時は事前に審査を受けなくてはいけない」というルールが厚生労働大臣によって定められています。
つまり、この13条のルールによって、遺伝子組換え食品には事実上、販売前に一律で審査を受ける規制がされているのです。先に出てきた話を踏まえると、「ポジティブ・リスト方式になっている」とも言えるでしょう。
この遺伝子組換え食品の規制を参考にすると、細胞培養食品も「食品、添加物等の規格基準」のなかで生産基準などを定めることによって、販売前に安全性のチェックをすることが可能かもしれません。ただし、これはあくまでも可能性の話です。今後、どのような法制度で細胞培養食品の安全性を確保するのか、消費者である我々も関心を持ちつつ、その動向を見守っていくことが必要です。